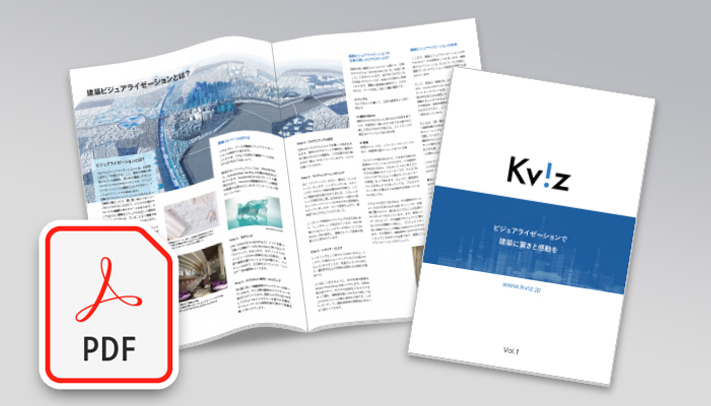2024年10月19日(土)に開催された「あにつく2024」より、「基調講演:絵コンテセッション」のセッション内容を紹介します。

セッション概要
基調講演:絵コンテセッション
毎回大好評の小松田監督による「絵コンテ」セッションが、今年は拡大版で登場!高いクオリティで知られる株式会社ウィットスタジオの浅野恭司氏と中武哲也氏をゲストにお迎えし、「WIT流アニメ制作の秘訣」からキャリア形成について、監督、作画監督、プロデューサーの立場から語っていただきます。また、明日から使えるノウハウや、監督たちが愛読する参考図書もご紹介します。
【主催】株式会社Too
【特別協賛】オートデスク株式会社
【登壇者】小松田 大全 氏
株式会社ウィットスタジオ 浅野 恭司 氏
株式会社ウィットスタジオ 中武 哲也 氏
株式会社サンジゲン 瓶子 修一 氏
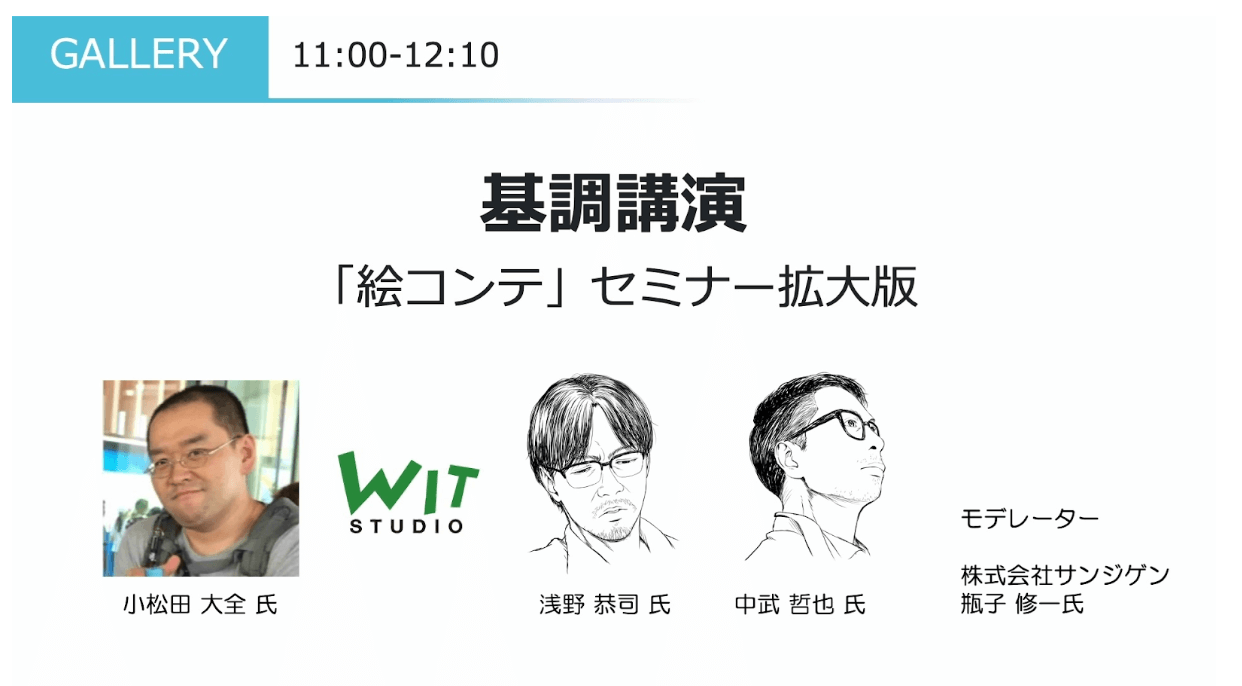
オープニングトーク
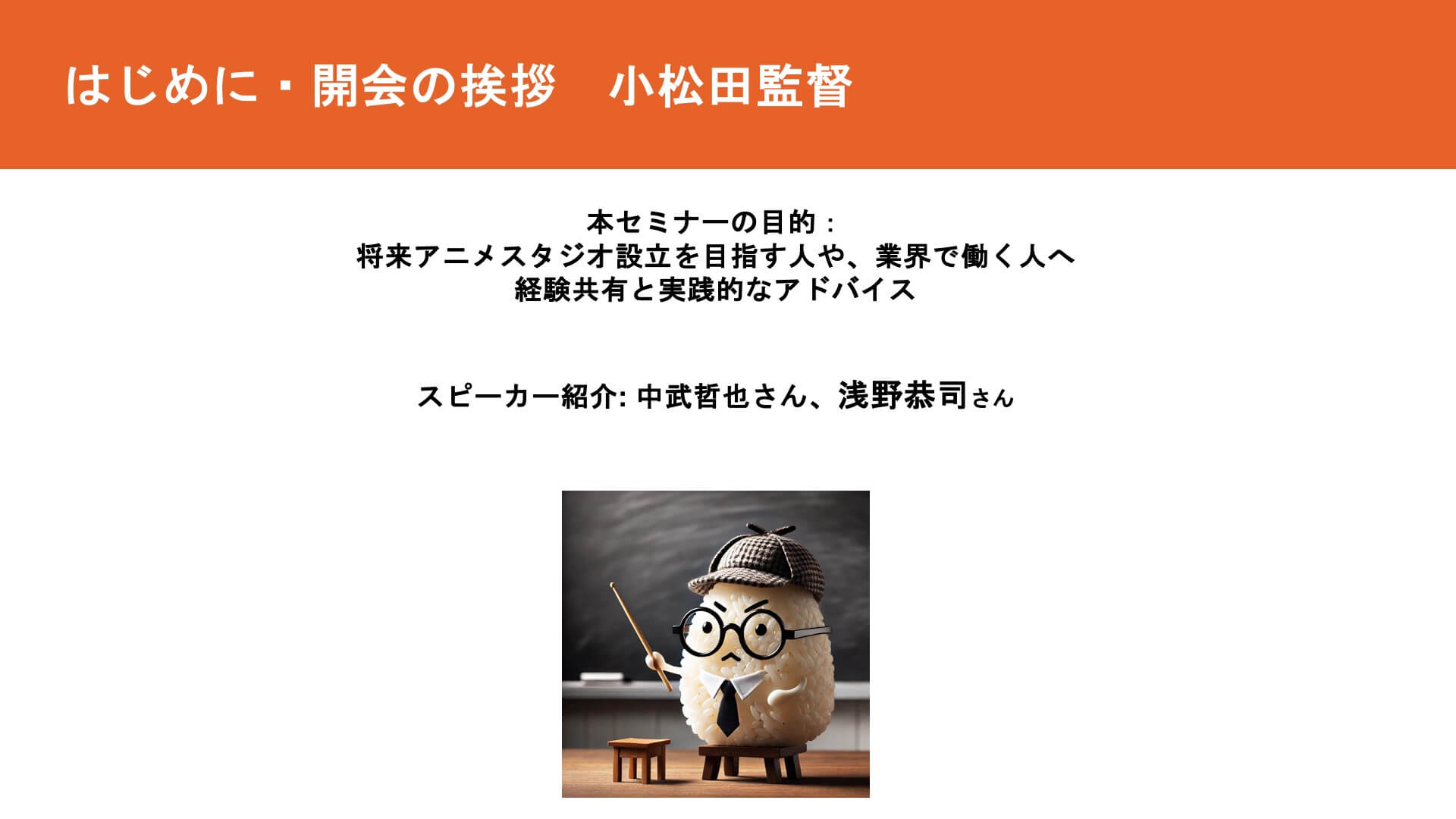
小松田:
今までも色んな話をしてきましたが、今回はその中でも役に立つことや、今日からできること、実際に役に立つことを話したいと思っています。よろしくお願いします。
「今回基調講演でいかがですか?」と聞かれた時に、やっぱり自分がこの業界で26年ほどやってきた中で伝えたいテーマは「サバイバル」、つまり「生き残る」ことだなと思いました。業界に入るのも大変ですが、入った後に生き残る方がもっと大変だと、実際に経験して強く感じています。
逆に言うと、プロになる前、業界に入ったばかりの頃、私は北久保弘之さんという監督にお世話になったんですが、その時に言われた言葉が印象的でした。「プロになったら、その時は会社に席を用意してもらえると思う。でも、その席を1年後も用意してもらえるかどうかは君の実力次第なんだよ」と。
若い自分にとっては、プレッシャーの大きい言葉でしたし、正直、不安を抱えながら進んでいきました。ただ、実際に仕事を続けていくなかで、例えば私の場合は『エヴァンゲリオン』の新劇場版をやらせてもらって、1本終わった後にまた声をかけてもらえました。これは、自分がやりたい仕事を次もお願いされる、いわば「サバイバル」を続けられたからなんだなと思います。
ではどうして生き残れたのかと振り返ったとき、今回のゲスト、ウィットスタジオの浅野恭司さんと中武哲也さんの存在が大きかったです。浅野さんは、私がプロダクション・アイジー(以下、I.G)に入った時の2年先輩のアニメーターで、中武さんは2年後輩で制作進行として入ってきました。私たち3人が出会ったのは、今からほぼ四半世紀前、25年近く前のことです。
当時の私はとにかく絵が下手で、『攻殻機動隊』の作画監督の黄瀬和哉さんのスタジオで、「君は、絵の勉強が足りていないぞ」と指摘を受けるばかりで原画試験にも全然受かりませんでした。でもその時、浅野さんに相談に行くと、私の下手な絵を見ても優しく話を聞いてくれて、前向きなアドバイスを沢山いただきました。
そんな数々の思い出を振り返って思うのは、生き残るためには「本音で仕事の話ができる同世代の仲間」と出会うことが大事ということです。皆さんも、スタジオで机を並べている人や専門学校のクラスメートが、そういう仲間になるかもしれません。そうした人たちと仲良くなって、自分の好きなアニメーションについて語り合うことが、実はサバイバルの中で一番重要なんじゃないかと改めて感じています。
だからこそ今回、浅野さんと中武さんといろいろな話をしようと思っています。

I.G時代の3人と独立

瓶子:
モデレーターを務める瓶子です。実は皆さん、昔はI.Gで一緒に仕事をされていたんですよね。そこから、どうして独立することになったのか、ぜひその辺りの経緯を伺いたいです。
浅野:
私がIGに入ったのは1996年です。当時、エヴァンゲリオンがものすごい話題になっていて、アニメの未来を感じた時期でした。その頃、私は代々木アニメーション学院に通っていたのですが、クラス中が「ガイナックスに行きたい!」って盛り上がっていました。
正直自信がなかった私はどうしようかと悩んでいたら、学校の先生が「プロダクション・アイジーに行けば?」と勧めてくれたんです。I.Gは『パトレイバー』を手掛けていた会社で、私も大好きだったので受けてみたら、ありがたいことに採用していただけました。それで1996年に入社したという流れです。
中武:
私が入社したのは2000年です。I.Gでは、ゲームのアニメーション制作をしているチームに入りました。ラッキーだったのは、そこでフリーの優秀なアニメーターたちが集まるという恵まれた環境にいれたことです。松竹徳幸さん、海谷敏久さん、西村博之さんといった名だたる方々と一緒に仕事をすることができました。
当時、ラッシュチェックを通して、自分たちが描いた絵が本当に動いているのを見るのが感動的で、「アニメって面白い!」と思ったのを今でも覚えています。良い環境に恵まれたおかげでそのまま続けてこれて、気付けば25年目になりました。
小松田:
もし私たちがI.Gで本当にやりたいことを全部達成して満足してしまっていたら、おそらく今もI.Gにいたんじゃないかと思うんです。
私は、2003年頃にフリーランスになりました。一方、中武さんと浅野さんはI.Gに残り、素晴らしい作品を作り続けて、2012年にウィットスタジオとして独立されましたよね。その話を聞いたとき、すごく不思議に思ったんです。「I.Gであれだけ質の高いアニメを作っていたのに、どうしてわざわざ独立しようと思ったんだろう?」と。改めてお聞きするんですが、独立する必要性や目的は何だったんですか。
浅野:
独立のきっかけは、やっぱり新しいことをやりたいという気持ちが大きかったですね。元々I.Gで中武と一緒に仕事をした時に、深夜のファミレスで「将来こんなアニメを作りたい」や「独立すべきかどうか」なんて話をよくしていたんです。
中武:
私も、新しいことへの好奇心がすごく強かったのだと思います。ちょうどその時期、『君に届け』や『戦国BASARA』といった作品を続けて手掛けていたんですが、同じ作品が続く中で、新しい挑戦をしたい気持ちがどんどん出てきたんです。
浅野:
その頃、私は『君に届け』と『戦国BASARA』を交互に担当していました。その後、『ギルティクラウン』で荒木哲郎さんと一緒に仕事をするなかで、自然と優秀なスタッフが集まりました。そのメンバーがウィットスタジオの立ち上げ時の中心メンバーになっています。
小松田:
その新しい挑戦のひとつが、進撃の巨人のPVですよね。当時そのPVを見た時に、「これまでの制作体制ではできなかったことに挑戦するために独立したんだろうな」と感じました。
浅野:
そうですね。『進撃の巨人』では、PVでのワンカットのアクションシーンがアニメーターのモチベーションを爆発させました。その結果、スケジュールが厳しくなって大変でしたが、その情熱が作品のクオリティの高さに繋がったと思っています。
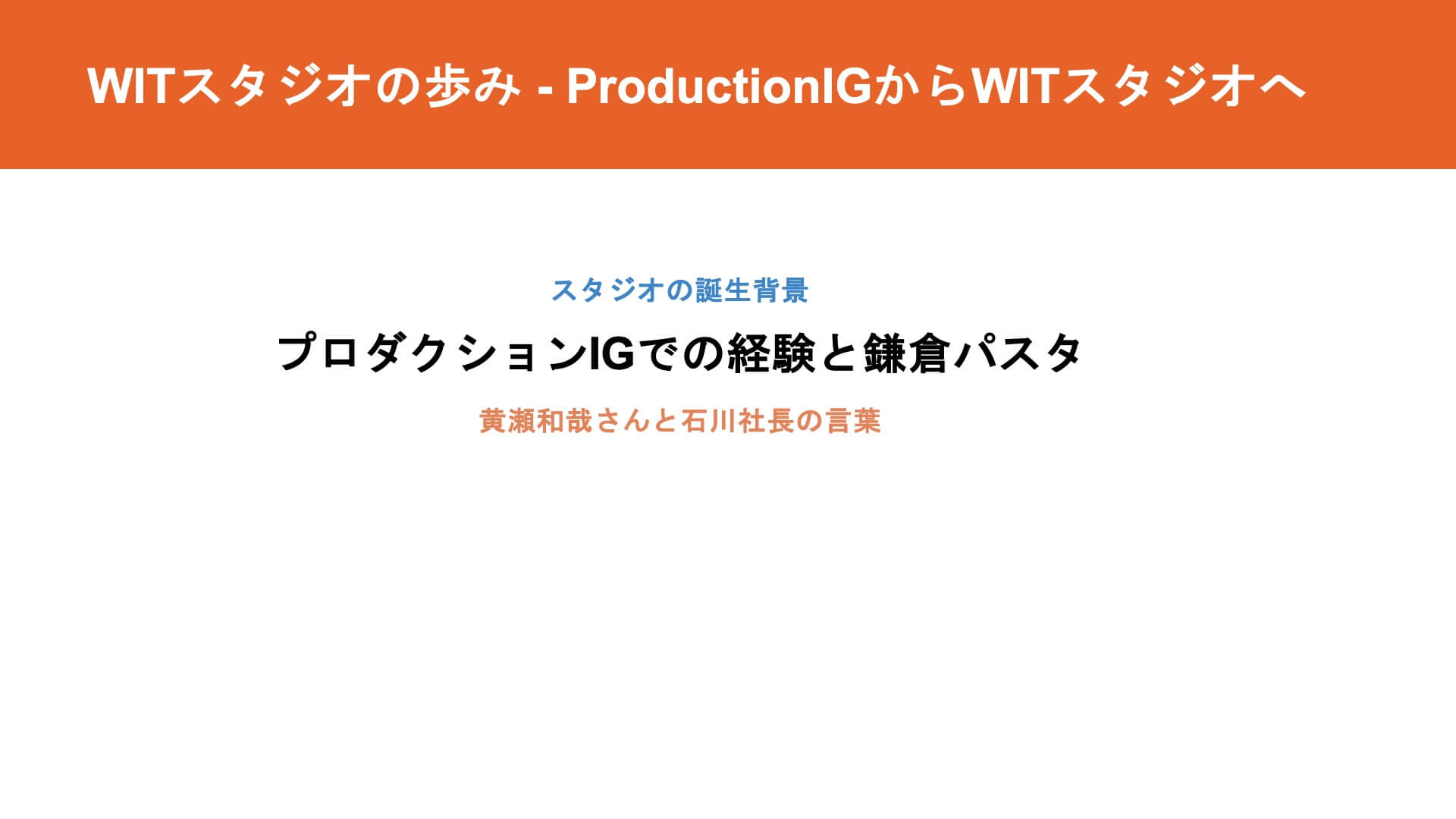
瓶子:
独立のタイミングで『鎌倉パスタ事件』が起こったという話を耳にしましたが、その説明をお願いしてもいいでしょうか?
中武:
この鎌倉パスタ事件というのは、私たちが「I.Gから独立したい」と思った動機から始まります。新しい環境で、今まで一緒にアニメを作ってきた仲間たちと、新しいアニメーションを作りたいっていう好奇心が原動力でした。
一方で、いきなり「会社辞めます」と言ってしまうと、I.Gに大きなダメージを与えちゃうじゃないですか。そこで、独立の1年以上前に石川社長に時間をもらって話をすることにしたんです。石川さんってそういう時、危機を察知する能力がすごいんですよ。「あ、この人話しづらい話をしようとしてるな」と感じ取られていたと思います。
小松田:
石川さんは、嫌な話が来そうだと思ったらそれを未然に防ぐのが上手いんですよ。そういう話ができないような場所に連れ出しちゃったりするのが良い例です。

中武:
まさにそれです(笑)。「じゃあ、今から鎌倉行くか」と言われて、「今から鎌倉ですか!?いいですね!」という感じで。粋なことを言うなぁと思いながら、車に乗りました。
そのときに、一緒に行ったのが和田丈嗣です。今のウィットスタジオ代表で、現在はI.Gの社長でもあります。和田と私の二人が石川さんの車で鎌倉に連れて行かれると思ったら、着いたのは鎌倉パスタだったんです(笑)。
中武:
ランチを食べていると石川さんに「何か話したいことがあるんでしょ?」って聞かれたので、思い切って「和田と浅野と私で、独立したいと思っています」と伝えました。そしたら、石川さんは既に答えを用意していたんですよ。「会社を作りたいのか、作品を作りたいのか、どっちだ?」と聞かれたので、即答で「アニメが作りたいです」と答えました。
中武:
その場で石川さんから、「じゃあ金は俺が出すから、一緒にやるのはどうだ?」という話が出てきました。その時に石川さんの提案を断って独立していたら、今のウィットスタジオは無かったでしょうし、和田がI.Gの社長になることもなかったかもしれません。
直感的に、石川さんの思いを受け入れる方がいいなと思って、I.Gグループ内の新しいブランドとしてウィットスタジオを立ち上げることにしました。これが、私たちのなかで『鎌倉パスタ事件』と呼んでいる出来事です。
小松田:
私のときは、フリーランスになることを石川社長に伝えたらそんなドラマティックなこともなく、「小松田君はフリーに向いてると思うよ」って軽く送り出されましたけどね(笑)。でもお二人の挑戦があったからこそ、今のウィットスタジオの成功があるのだと思います。
中武:
私たちはアニメを作ることだけが得意で、それ以外のことは苦手なんですよね。当時会社を作る時に、バックオフィスの仕事など、仕事ができる環境整備をしてくれるスタッフがいなくて本当に困っていました。パソコンのスペックや周辺機材から何から何までですよね。当初はひたすらパソコンや棚を買ったりしてました。
小松田:
実は、そういうところが一番大変なんですよね…。トリガーが独立したときも、最初のスタジオに行ったら、社長の大塚雅彦さんがずっと椅子を組み立てていて、「椅子の組み立てが本当に嫌です。椅子じゃなくてアニメが作りたい(笑)」と言っていたことを思い出しました。
中武:
弊社でも、私たちに加えて荒木哲郎さんや牧原亮太郎さんという監督の方々も、みんなで棚を作ってくれていました。今思うと、本当に手作り感満載のスタートでした。

代表作「進撃の巨人」
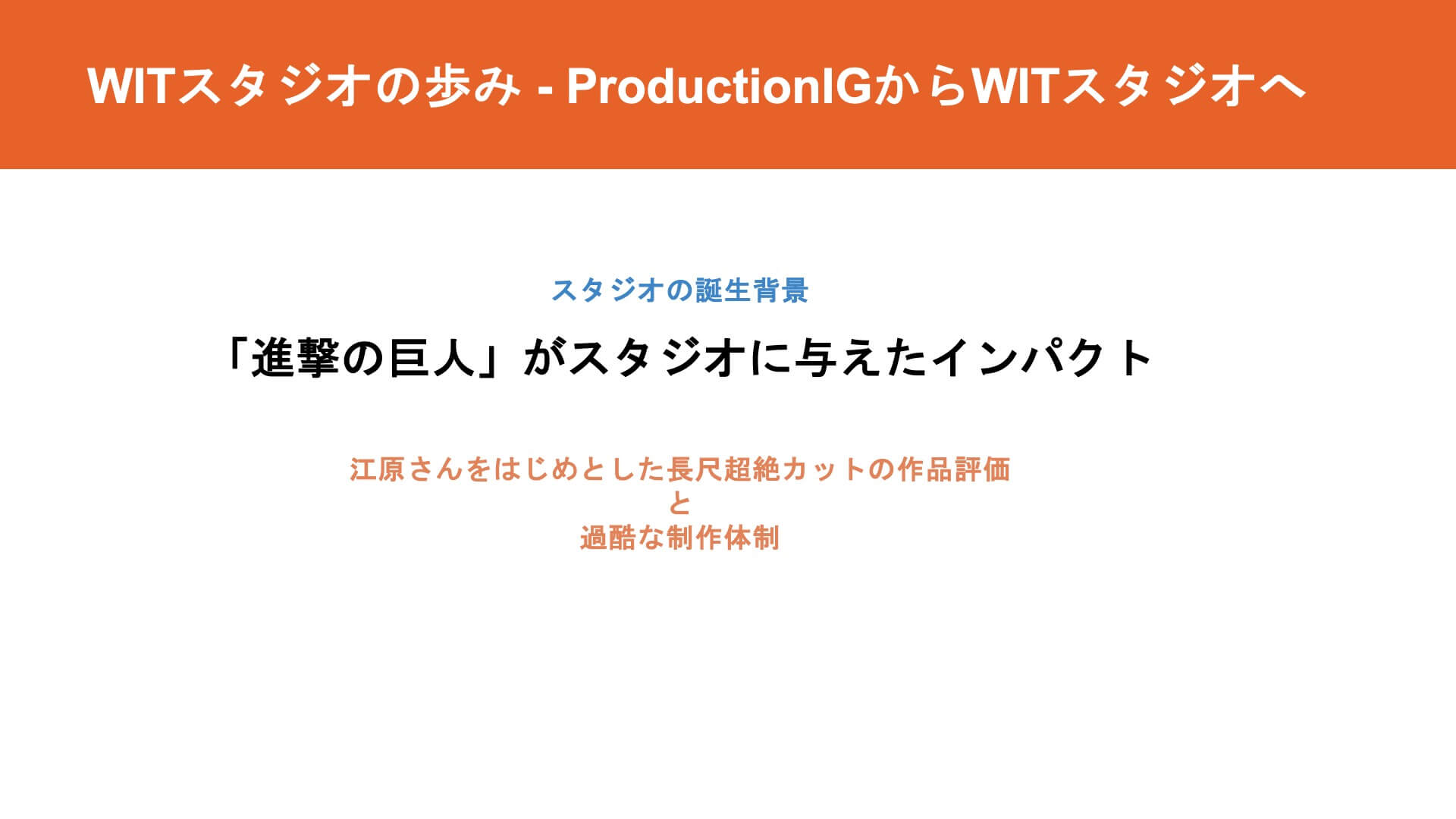
瓶子:
ウィットスタジオが出来たタイミングで、すぐに進撃の巨人の話があったと伺っています。進撃の巨人が、この業界にどんな影響を与えたのか、小松田さんがPVを見て「すごい!」と言っていた話もあったので、その辺りを詳しく教えてください。
小松田:
私の知り合いのプロデューサーが、こんなことを言ってたんです。「彼らは墓穴を掘ったよ。あんなハイクオリティなもの、シリーズで作れるわけがない。一番最初に最高のものを出しちゃったから、それ以降はクオリティが下がる一方だよ。彼らは失敗したんだ」と(笑)。
瓶子:
確かにそんな話もありますよね。視聴者から見ても、あのPVだけでもすごいインパクトを感じましたよね。この進撃の巨人のPVのカットも、その一つだと思います。
神作画 – 戦闘シーン | 進撃の巨人 | Netflix Japan
https://www.youtube.com/watch?v=d4U1WcIM1E8
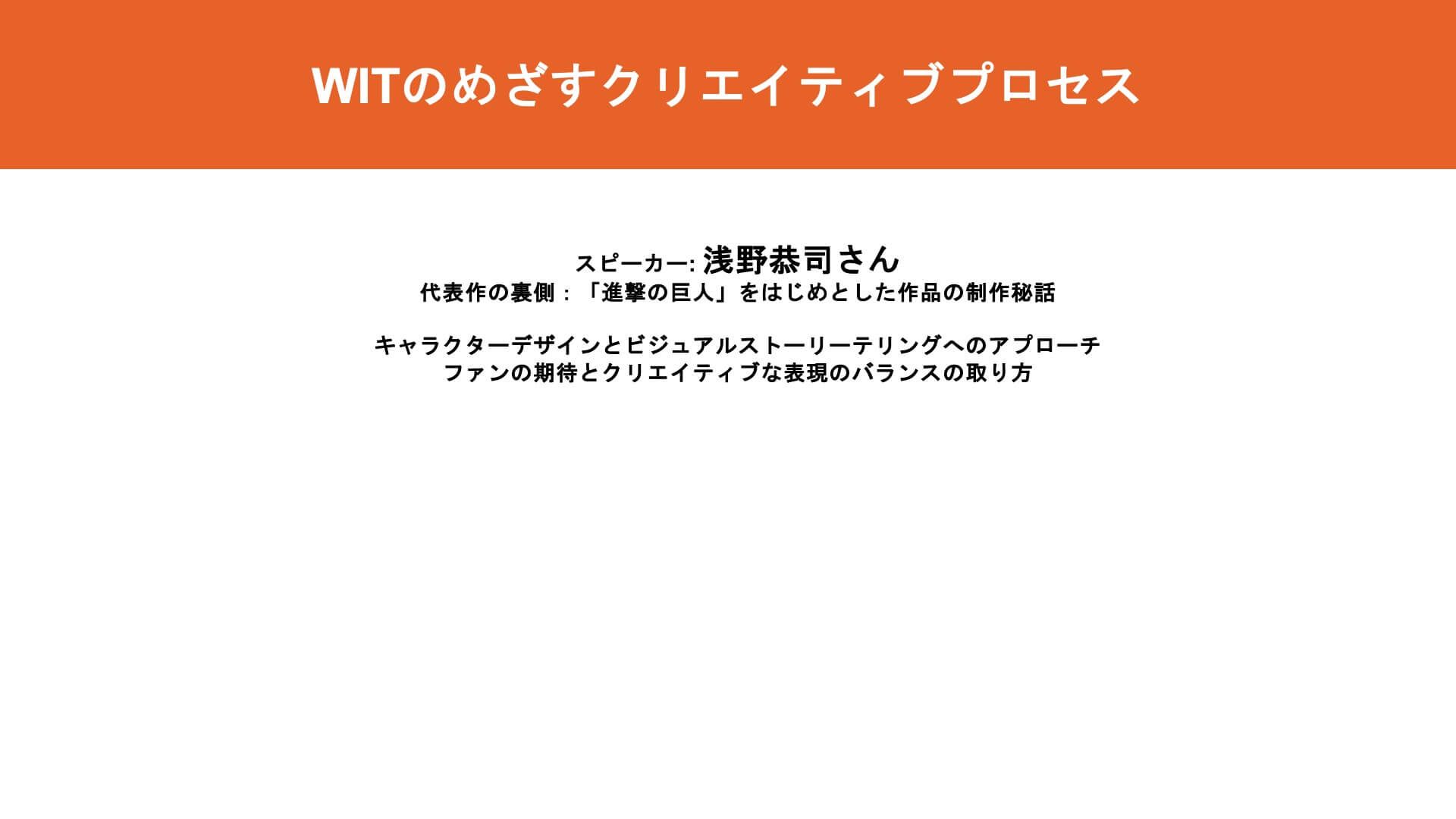
浅野:
このPVの時に、先行してワンカットのアクションシーンを作ったんです。それが逆に裏目に出たというか、アニメーター全員が「これがやりたい!」って思い始めちゃったんですよね。この11話のアクションが爆発的にすごくなるんですが、それまではあえて枚数を抑えて我慢していたんです。でも、PVでは前借りする勢いで全力を出してしまって、その流れでカロリーが高いシーンがどんどん溜まっていきました(笑)。
中武:
この回は私たちの中で『スーパーカロリー回』と呼ばれていて、本当に圧縮されすぎているんです。期間が短い中でカロリーが溜まりすぎると、テレビシリーズ全体を作るのがすごく苦しくなってしまうんですよ。だからこそ、この爆発的なシーンが来るまではかなり抑え込んで、「ここで一気に爆発させる」というような作り方をしていました。

浅野:
最初はワンカット処理の予定ではなくて、絵コンテでは普通の処理でした。ただ江原康之さんのアイデアで「これ、ワンカットにしませんか?」ということになって、結局江原さんが泊まり込みで作業して仕上げることになりました。
ワンカットのインパクトって大きいと思うんです。もっと世に出てほしいなと思っています。世間からアニメーターがもっと注目されてほしいんですけど、実際にはなかなか名前が出ないんですよね。
このワンカットが地上波のテレビで「伝説の18秒」として取り上げられた時があったんです。私は「これで江原さんも有名になるぞ!」と思っていたのですが、江原さんの名前が出るところはありませんでした。正直、「なんだよそれ」と思って、アニメーターの価値がまだ低く見られているんだなと、そのときに感じました。
小松田:
基本的にアニメーターって目立ちたがり屋なので、大変なカットを振られても挑戦しちゃうんです。そういうのが、また新しくてすごいとされるシーンを生み出すんですよね。
例えば、私はアニメージュ連載をやっているんですけど、そこに板岡錦さんを呼んだ際、彼が描いたプリキュアの変身バンクについて話を聞きました。緩急のはっきりした動きが特徴的で、志田直俊さんの影響が大きいのだろうと思ってたんですが、実際本人に聞くと、やはりその通りでした。アニメーターは、憧れの人を追いかけながら成長していくんだなと思いました。
同期や先輩にも必ず自分より上手い人がいて、悔しさを感じながら成長していくんです。私の同期に『ワンパンマン』のキャラクターデザインをしている久保田 誓 君がいます。彼が同期にいるってだけで、もう絶望的な気持ちになるんですよ(笑)。
ある時、どうしたら上手くなるのか久保田君に相談したら、「自分の実力が評価される現場に行った方がいいですよ」と言われてしまいました。逆に、そのアドバイスを全く聞かずに、不相応な無茶な現場に飛び込んでいきましたけどね。結局、その無茶な経験が今の自分を支えていると思っています。ポジティブな言葉ももちろん大事ですが、ネガティブな言葉に対抗するパワーがすごく大事なんです。
アニメは、1人のアニメーターだけではなく、先輩や同期、後輩のみんなが連続的に影響し合いながら進化していくものです。だから、「このカットすごいな」と思うことがあったら、その人がどういう影響を受けてどんな背景があるのかを知ると、アニメがもっと面白くなると思います。
若手の育成と業界の未来

瓶子:
すごいカットを作るアニメーターの方がいた、机を作るのが大変だったという話もありました。一方ウィットスタジオが進んでいく中で、若手の育成についてどう思われますか?
浅野:
私はI.Gにいた頃から採用面接に出て若手と話したり、面倒を見てきたりしたんですけど、正直なかなか上手くいきませんでした。I.Gにいる時から、「育成って難しい」と感じていました。一方で、若手を入れないと会社が活性化しないため、当然採用は続ける必要があります。正直手探りの状態だったので、I.Gの時のやり方をそのままウィットでも続けていました。ただ、それだと上手くいかないんですよね。
結果として、10年ほど経ってもそこまで多くの若手が残ってくれませんでした。しかし、アニメ制作には多くの人が必要なので、採用を止めるわけにもいきません。そこで、育成方法について思いついたのが、「動画と原画で採用枠を分ける」というやり方でした。
そうしようと思った理由は、アニメーターになりたいのほとんど人が「原画を描きたい!」という想いを持っているからです。しかしながら、どこの会社であってもまず動画からスタートして、動画で技術を学び、その後に原画試験を受けて原画デビュー、という流れが一般的なんです。
ところが、この流れだとせっかく動画の技術を身につけた人が原画になってしまうので、動画をやる人がいなくなってしまいます。そこからまた新人を採用して、動画を一から教えるというサイクルになってしまう訳です。その結果、動画の技術レベルが全体的に上がらないという悪循環なんです。
そこで、思い切って動画と原画の採用枠を完全に分けることにしました。そうすると、「アニメには関わりたいけど原画は少し自信がない」という人が、動画として働きたいと応募してくれるようになったんです。そういう人たちが入ってきてくれるようになって、動画の技術が安定してきました。
現在のウィットスタジオは、動画が50人弱、原画が30人弱くらいの体制になっています。この採用方法はとても上手くいっていて、さらに今年度からは全員を契約社員にしました。以前は業務委託契約が多かったんですが、すべてを社員化することでお給料も安定させることができ、離脱する人を減らすことができました。

他社と協業した理由
瓶子:
ウィットスタジオで若手を育てているという話でしたが、その前にはI.Gが作画塾みたいなかたちで、グループとしてアニメーターを育てていたというお話も聞きました。そんななかで、中武さんに伺いたいのは、「スパイファミリーで、ウィットスタジオがCloverWorksと共同制作をしたことについて」です。業界では珍しいことだと思うのですが、どうして他の会社と一緒に制作するかたちを取られたのでしょうか?
中武:
今の時代は、10〜15年前と比べて業界全体で作品数が増えています。しかし、クリエイターの数がそこに追いついていない状況にあります。スパイファミリーのシーズン1は全25話でしたが、それを連続で単独のスタジオで作り続けるのは今の業界では正直かなり厳しいのが現実です。視聴者としては連続で2クール観たいという気持ちがあると思いますし、作品への話題性を考えてもなるべく短いスパンで制作したい。だからこそ、仲間が必要になるんです。
今回、スパイファミリーでは、CloverWorksの福島祐一さんというプロデューサーとお話しして、一緒に制作するという選択をしました。お互い元請けができる会社同士なので、条件設定もきっちり半分ずつにしました。契約書や予算表も全部オープンにして、真実の数字を共有して、序盤から丁寧に進めたんです。そうやって、争いが起きないようにしました。
スパイファミリーは、今も継続的に制作を続けています。2023年の10月にシーズン2を1クール放送しましたが、その終わりのタイミングで劇場版を公開しました。劇場版の制作は、会社単独では絶対にできません。テレビシリーズで盛り上がっているタイミングで映画を投入することは、私たちとしても初めての大きな経験となりました。その結果、興行収入が60億円を突破し、これはウィットスタジオとしては本当に初めての規模感のお仕事でした。
いいアニメをたくさん作るということは、クリエイターたちにとっても大事なことです。そしてお金が返ってくれば、きちんと給料を支払うことができる。そこには大切なことが詰まっていると思います。
小さな尺を単独で丁寧に作るのも素晴らしいですが、アニメーションを通してもっと多くの人を幸せにするには、たくさん作らなければいけません。そのためには協業が必要であり、スパイファミリーはその象徴的なプロジェクトになりました。
中武さんに質問!
「浅野さんとタッグを組んで会社を作った理由は?」
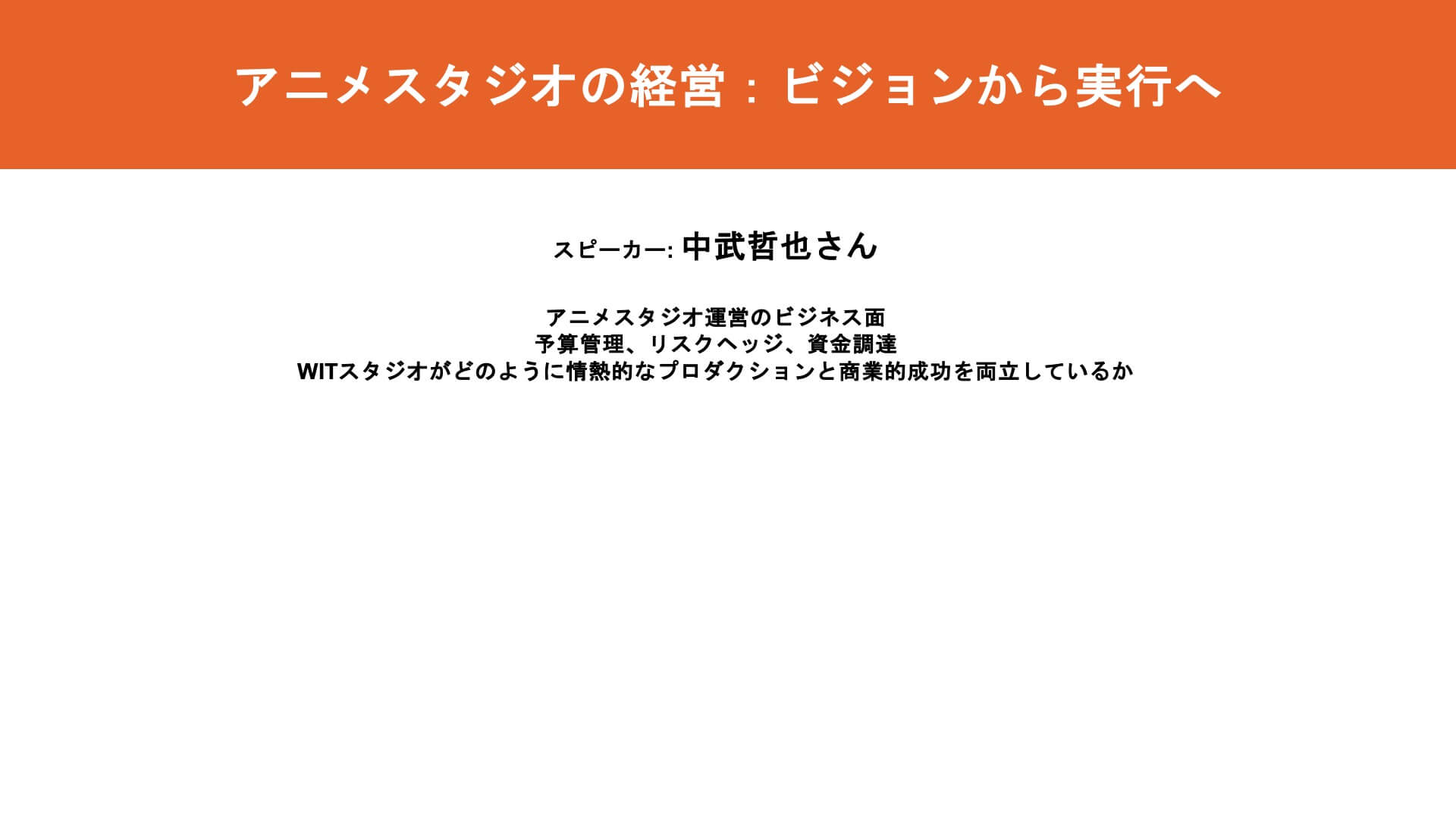
瓶子:
中武さんに質問です。I.Gで制作をされていた時、作画監督の方などたくさんの人と仕事をされていたと思います。もちろん、浅野さん以外にもいろいろな方とお付き合いがあったはずです。その中で、なぜ浅野さんとタッグを組んで会社を作りたいと思ったのか、その理由を教えてください。
中武:
作品にとって大切なことの一つが納品、そして品質です。この2つを守るためには、やはり良質なクリエイターと一緒に仕事をしないといけません。浅野さんは絵がうまいだけじゃなく、締め切りに向けて最後に全体のバランスを取る能力がある方だと思っています。それと、何よりもいい人で、シンプルに話しやすいんですよ。

小松田:
これって実は本当に重要なことで、絵がうまい人って何かしら致命的な欠点を持っていることが多いと個人的には思っているんですね。でも浅野さんは違います。
私も原画が全然描けなくて困っていた時に浅野さんに相談したことがあるんですけど、しっかり話を聞いてくれるし、何より否定をしないんです。人間的にすごくできた人なんだと思いました。こんなに優しくて、人間的にも問題のない人って、この業界に多分5人くらいしかいないんじゃないですかね(笑)。その中の1人を捕まえて一緒に独立する、素晴らしい判断だったと思います。
中武:
私も本当に正しい判断だったと思っています。弊社の社員のアニメーターたちも、浅野さんが言うことなら聞いてくれるんです。私が何か言って反応が悪い時でも、浅野さんが言うとみんな納得するんです。やっぱり面白いし、目的に沿っている人と一緒にいたいじゃないですか。それが浅野さんだったということですかね。
浅野さんに質問!
「考えに変化があったのはいつ頃ですか?」

瓶子:
次に浅野さんに質問します。浅野さんも若い頃はスーパーアニメーターみたいに、原画で派手なアニメーションをやりたいと思っていたと伺いました。今ではさまざまなことをやられていると思いますが、その意識が変わったタイミングはいつ頃だったのでしょうか?
浅野:
私もアニメーターになりたくて専門学校に通い、I.Gに入って、その頃は「原画が描ければそれでいい」と思っていました。本当にそれだけで十分で、「キャラクターをデザインする」、「自分の絵柄を持つ」などは全然考えていませんでした。誰かが描いた設定をもとにしてそのキャラクターを動かす、それがただただ楽しくて、会社に泊まり込んで仕事をしても全然辛くありませんでした。
当時のI.Gは劇場作品やリアル志向の作品が多くて、それも面白かったんですけど、一方で他の会社、例えば、ガイナックスではガッツリ動くアニメをやっていて、そういうのもやりたいという想いはありました。それでも楽しかったのでモヤモヤはしませんでしたが、I.Gではそういう動く作品が少なかった分、心の中では激しい動きの作品をやりたいという気持ちもありました。
外部の仕事で、例えば『レッツ&ゴー』や『ハンターハンター』などのアクションシーンを描かせてもらうことでストレス発散、みたいなこともしていましたね。一方で、社内ではリアル志向の作品をしっかり作る。そこをきっちり両立させながらやっていました。
ただ、『攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG』が終わったタイミングで一旦区切りを感じて、どうしようかと思っていたんです。その時に中武がいるスタジオに移って、そこで作画監督やキャラクターデザインを任せてもらえる環境がありました。それまでは本当に「原画だけやりたい」という気持ちだったんですけど、そうやって他の仕事を経験していく中で、デザインの面白さにも気づくようになりました。
『進撃の巨人』や『PSYCHO-PASS(サイコパス)』でキャラクターデザインを任されるようになった時には、デザインの楽しさにどっぷりハマっていました。その辺りで、若い頃に思っていた「原画だけ描ければいい」という考え方から大きく変わっていきました。その時その時で、「面白いものは何か」と模索しながらやってきたことが、今の自分に繋がっているんだと思います。
小松田:
アニメーターとして原画をやりたいと思っても、原画だけで終わらないんですよね。作画監督やキャラクターデザイン、演出をやったりなど、原画以外の役割もやらなきゃいけないんです。原画だけでキャリアを貫くのは本当に難しいと思います。おそらく、それを達成しているのは井上俊之さんくらいじゃないですかね。
『ルックバック』の監督をしている押山清高君も、動画時代から他の人より圧倒的に長時間働いて、誰よりも早く上手くなった人です。彼も井上さん並みに上手い上で、監督として作品全体をまとめる仕事もしながら、原画を描く力も維持しているのは驚きです。
だから私たちも、原画だけをやりたいと思っても他の仕事もやらざるを得ないんです。でもそれは、同時に「作品を守る」ためでもあるんです。原作の絵柄を維持して、原作ファンが求めているアニメに仕上げる。その役割が、作画監督や総作画監督の仕事なんです。
浅野:
僕も若い頃は、スターアニメーターになることに憧れた時期もありました。でも今は、「作品を守ることが自分の役割だ」と考えて、仕事をしています。
オススメの書籍紹介
瓶子:
毎回このコーナーを設けさせてもらっています。1人ずつ、オススメの書籍を紹介していってください。まずは小松田さんからお願いします。
小松田氏:映画の撮り方・ビデオの撮り方 252本の名作シーンから解読するビデオ撮影テクニック
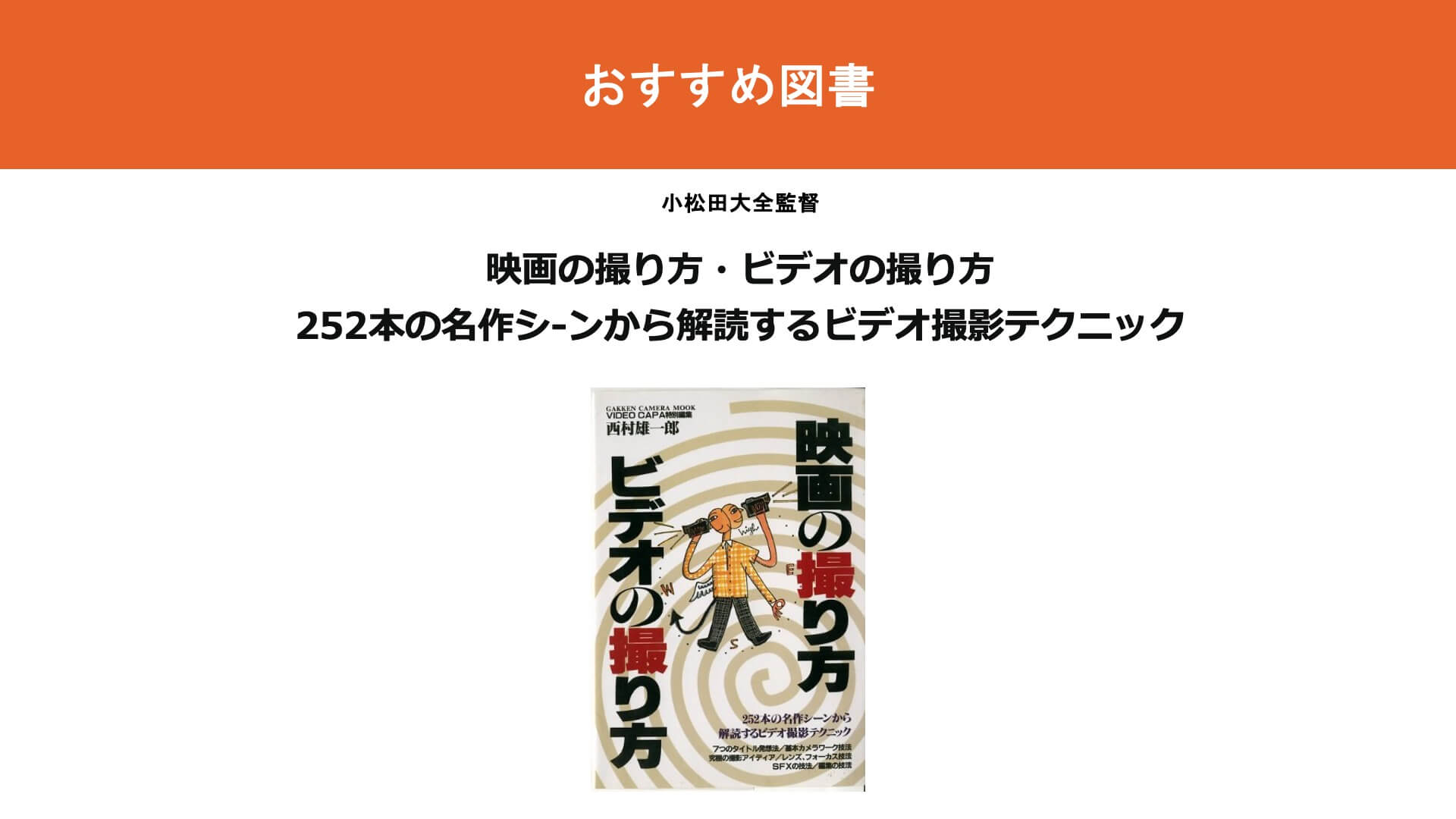
小松田:
今回紹介するのは、1995年くらいに私が愛用していた『映画の撮り方・ビデオの撮り方 252本の名作シーンから解読するビデオ撮影テクニック』という本です。映画のオープニングやアバンタイトルの演出にはどんなパターンがあるのか、時間経過をどうやって描くのか、オーバーラップをどう使うのか、そういったものを具体的な映画のコマを例に挙げて解説してくれています。まさに「映画の辞書」のような本で、私が絵コンテを描く時にもすごく役立ちました。
例えば、10年という時間経過をどうやって描くか迷ったとします。この本にはそういうシーンの参考例が載っていて、黒沢明監督の『姿三四郎』のエピソードが紹介されています。あるシーンで三四郎が稽古に励んでいるのですが、時間経過を表現するために「子犬が下駄で遊んでいる」というカットを挟むんです。その後また稽古シーンを挟んで、次に登場するのは成長した犬がボロボロの下駄を噛んでいるカットなんです。これによって「子犬が大きな犬になるくらいの時間が経った」って視覚的に示しているわけです。
こんなの自分では絶対に思いつかないと思いました。ただ、この本を読んだことで「あ、時間経過を描く時に動物を使うという手法があるんだな」と気づかされました。次に絵コンテを描く時には、「犬で時間経過を描けないかな」なんて考えたり。こういうふうに、先人の優れたアイデアがたくさん詰まっている本です。
浅野氏:METHODS 押井守「パトレイバー2」演出ノート
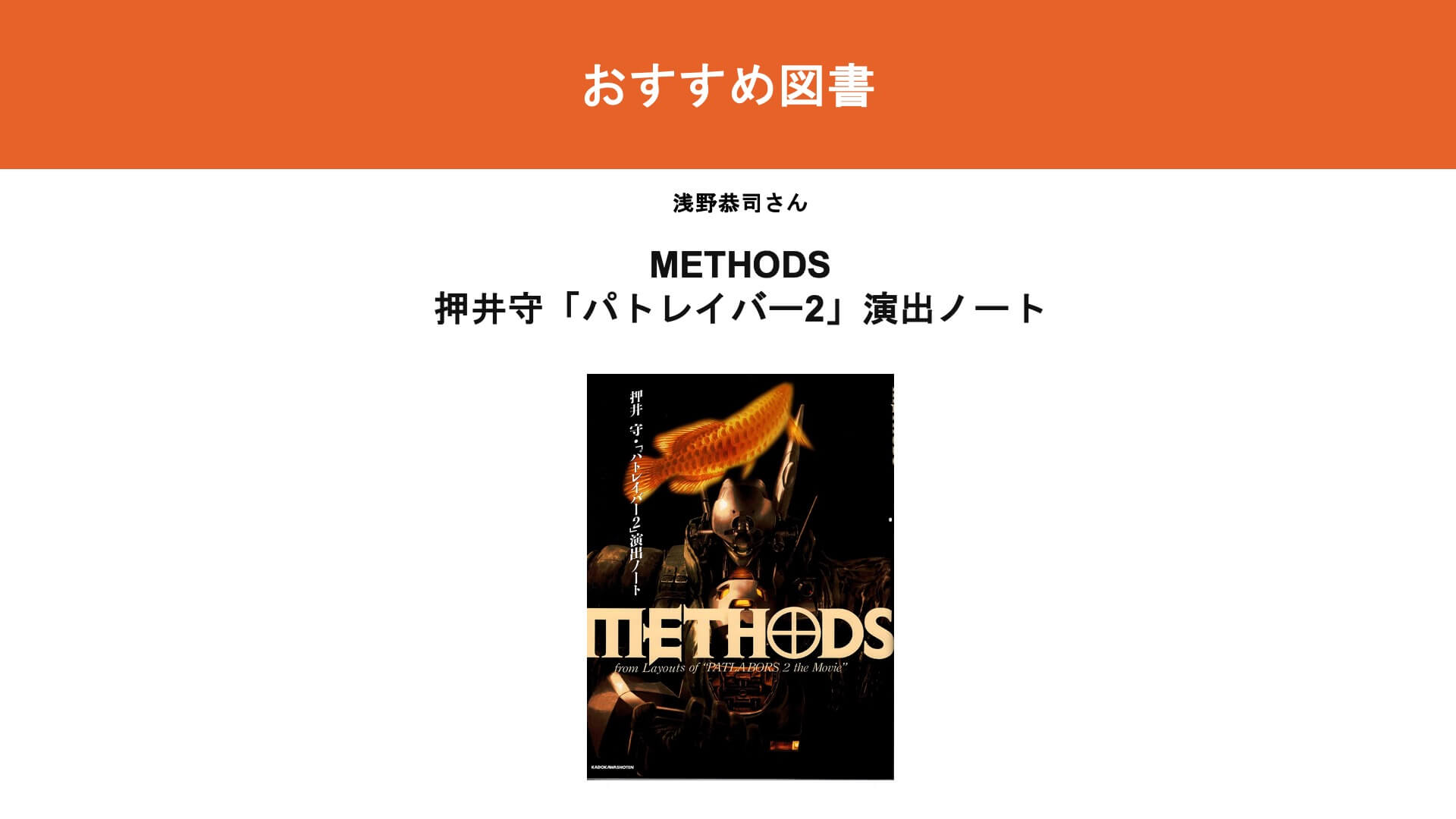
浅野:
これは、『METHODS 押井守「パトレイバー2」演出ノート』です。パトレイバー2が公開されたのは1993年で、この本が出たのが1994年になります。私はパトレイバーが好きだったので、1も2も見に行きました。アニメ雑誌にこの本が出ますと告知された時に、お昼代をつぎ込んででも買おうと決めて、実際に購入しました。
専門学校時代に手に入れて、中を開いて見たんですけどね。押井さんが1カットずつコメントを載せてくれてるんですよ。でも、私がまだアニメの現場で働いたことがなかったこともあって、当時は全然意味が分かりませんでした。ただ、載っている絵を見て「上手いなぁ」と思いながら眺めていました。購入当初はそんな素人目線で楽しんでいました。
アニメ業界に入って原画を描くようになると、レイアウトを描く機会が増えてきて、この本で押井さんが言ってたことが徐々に分かるようになったんです。ただ、まだ演出の仕事をしてなかったので、完全に理解するには至りませんでした。原画を描く時に「あ、こういうところに気をつけるべきなんだ」程度の感覚で少しずつ分かってきた感じです。
例えば、パトレイバー2の最初の方で、太田が若手を指導してるシーンがあるんですけど、土手の上からグラウンドを見下ろすカットなんですよね。手前に進士さんが立っていて、佐久間教官がしゃがんでいる。その奥に太田や若い隊員たちがグラウンドを走ってるカットなんですけど、押井さんがコメントでこう書いてたんです。「こういうカットは、手前の人物と奥の人物の対比が難しい。手前の人物が巨人みたいに見えてしまうんだ」と。
「それを防ぐためには、まず佐久間教官を一度立たせてみて、そのパース線上に移動させて、奥の人物との等身を確認しながら調整する」、と書いてあったんです。でも当時の僕は、「立たせるってどういうこと?」、「パース線ってどうやって使うの?」という感じで全然分からなかったです。今では当たり前に考えられることで、レイアウトを描く時には自然にやっている作業になります。当時は本当に謎だらけで、それを解明していくプロセスが個人的にすごく感動的でした。
この本には映像の解説以外にもそういう細かいポイントが詰まっているので、本当に勉強になります。映像そのものは『パトレイバー2』のDVDで見られますし、演出ノートも手に入ります。さらに、リミテッド版のDVDには絵コンテが付いてるんです。それらを組み合わせて見ていくと、押井さんが絵コンテの段階でどういう意図を持っていたのかが分かるので、その解釈がアニメーターにどのように伝わって、それが映像としてどのような形になっているのかが確認できます。
小松田:
余談ですが、この本は定期的に『復刊ドットコム』で復刊されています。その度に私も10冊ほど買って、現場の若手に配っています。個人的に、この本は業界のレイアウトレベルを底上げするための必須アイテムだと思っています。
中武氏:雑草魂 アニメビジネスを変えた男
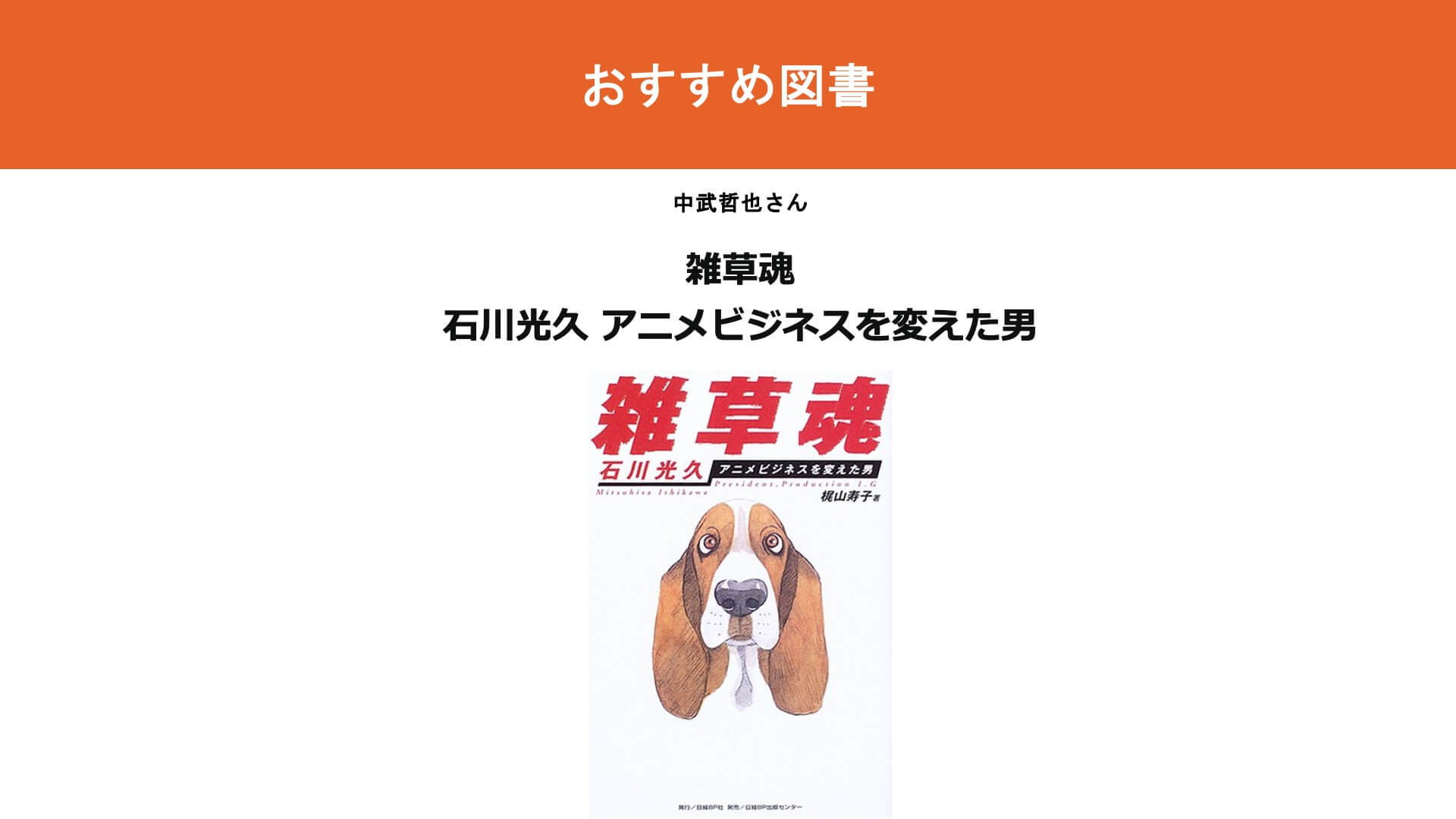
中武:
私がオススメする本は『雑草魂 アニメビジネスを変えた男』です。この本は、I.Gの石川光久さんが2006年までに歩んできた道のりを記録したものになります。2004年に公開された『攻殻機動隊 イノセンス』がカンヌ映画祭にノミネートされたのですが、そのカンヌに押井守さんと石川社長が赴いたエピソードや、その裏側の制作秘話が詳しく書かれています。それ以外にも、スタジオの立ち上げから石川さんのキャリアのスタート、どんな考えで今の姿を築き上げてきたのかが描かれている本です。
また、DVD限定BOXに入っている『宣伝、公開、そしてカンヌへ』というメイキングのDVDがあるのですが、これもすごく貴重な資料です。それも併せて見ると、何もないところからアニメ会社を立ち上げて、さらにアニメ業界初の株式上場を果たし、自分たちの力でカンヌ映画祭の舞台に立った男の記録が見られるんです。
今の時代はまた大きく移り変わっていますが、この本には、熱い気持ちを持って一生懸命アニメを作り続ける人たちへの応援や、どんな発想で自分たちの制作環境を変えていったらいいのかといったヒントが詰まっています。「いいアニメを作りたい」、そんな情熱は今も昔も変わらないということなんですよね。
この本も絶版で手に入りづらいのですが、見つけたらぜひ手に取ってみてほしい一冊です。
アニメ業界の今後
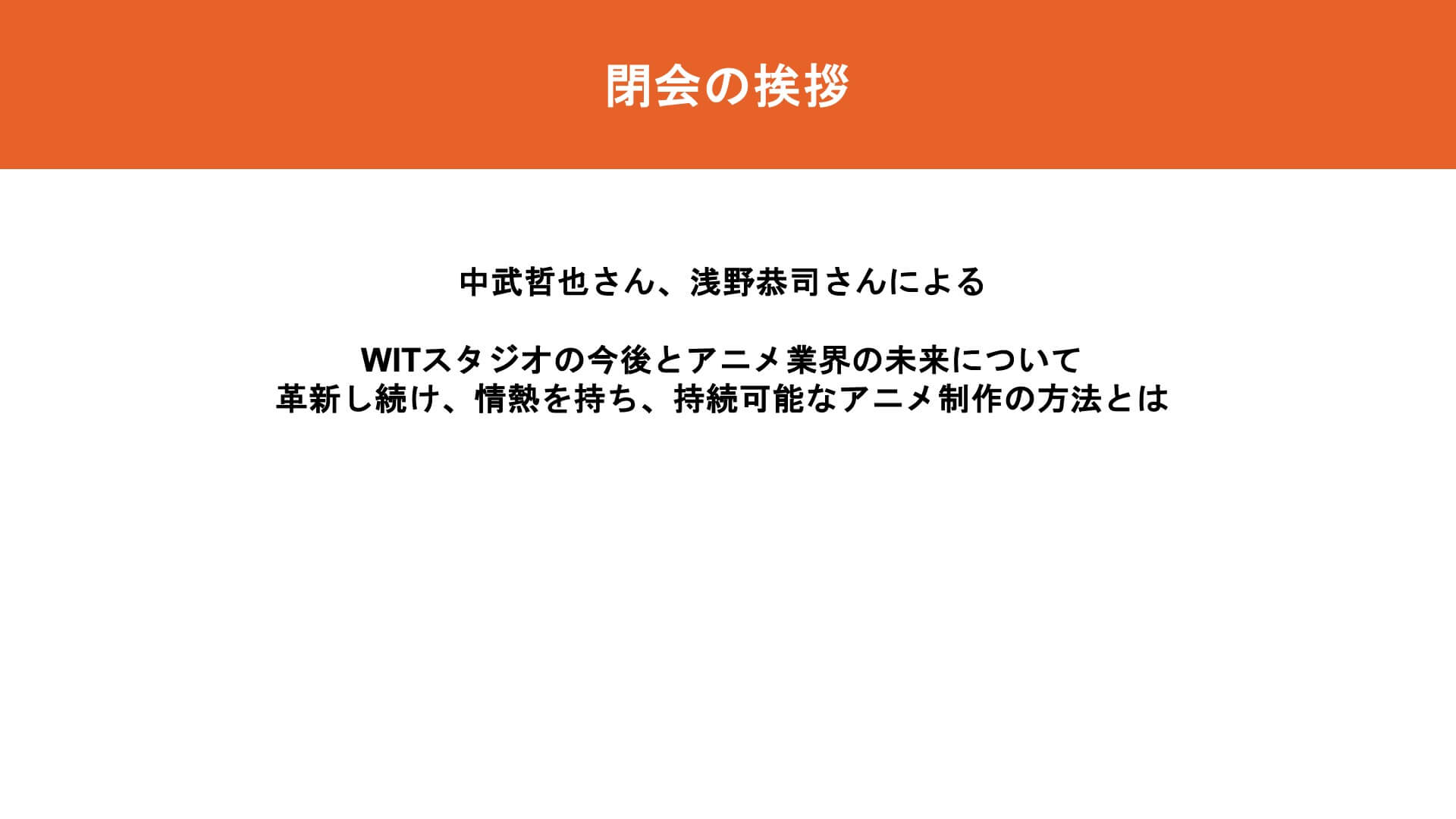
瓶子:
では最後に、中武さんと浅野さんに今後のアニメ業界についての予想や、お二人が今後どのように業界を生き抜いていくか教えてください。未来のアニメーターへのメッセージもあれば併せてお願いしたいです。
中武:
アニメ業界の未来についてですが、今私たちが取り組んでいることを例に挙げると、制作費だけでスタジオを回すのはかなり難しい状況です。そのため、制作を受注する前に条件交渉をしっかり行うのがとても大事になっています。交渉をクリアしても、スタッフに十分な給料を支払わなければならず、コストはどんどん増えるという状況です。
そこで、ウィットスタジオとしてはヒット作品を生み出して、その関連グッズやマーチャンダイジング事業を通して売り上げを拡大する作戦を取っています。いわば「いいアニメを中心にした収益構造」を作るという方向性です。
未来を考えると、原作の選び方も非常に重要です。その原作が映像化でどれだけ映えるか、商品化の可能性がどれだけ広がるかを見極め、それを最高のアニメーションで届けることが、今後の成功の鍵だと思います。
浅野:
アニメーターを目指している方や、すでにアニメーターとして働いている方にお伝えしたいことがあります。先ほども話しましたが、ウィットスタジオでは育成に力を入れていますが、今ではウィットに限らず、いろいろなアニメ会社が社員化を進めています。ですので、会社を選ぶ際には、しっかり調べて条件を見極めてほしいです。
「この会社じゃなきゃダメ」と思い込みすぎず、柔軟に考えることも大事です。例えば、最初に選んだ会社で得た経験が、後にフリーランスになった時や他の会社で働く際に繋がることもよくある話です。
もちろん「この作品が好きだから」や「このアニメーターが好きだから」という動機も大事です。ただ、今は条件や環境が昔と比べてかなり変わってきているので、そこもちゃんと調べた上で、自分に合った会社を選んでほしいと思っています。
瓶子:
みなさんのお話を聞いて、業界で生きていくためのヒントがたくさん得られた気がします。個人的にもすごく楽しかったです。またこういうセッションを開けたらいいなと思いますし、次回はアニメの監督をテーマにしたセッションなども出来たら面白いですね。